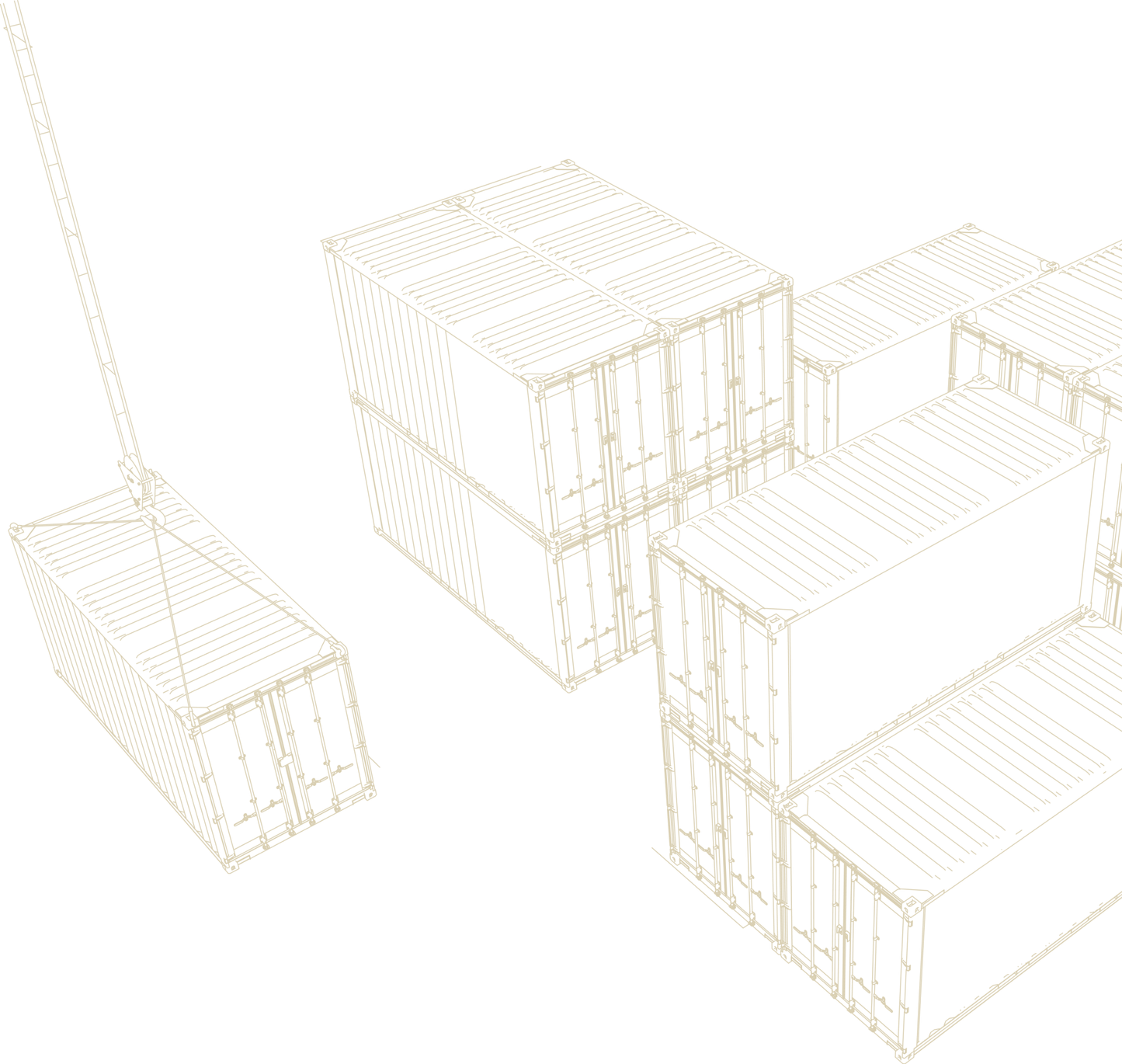
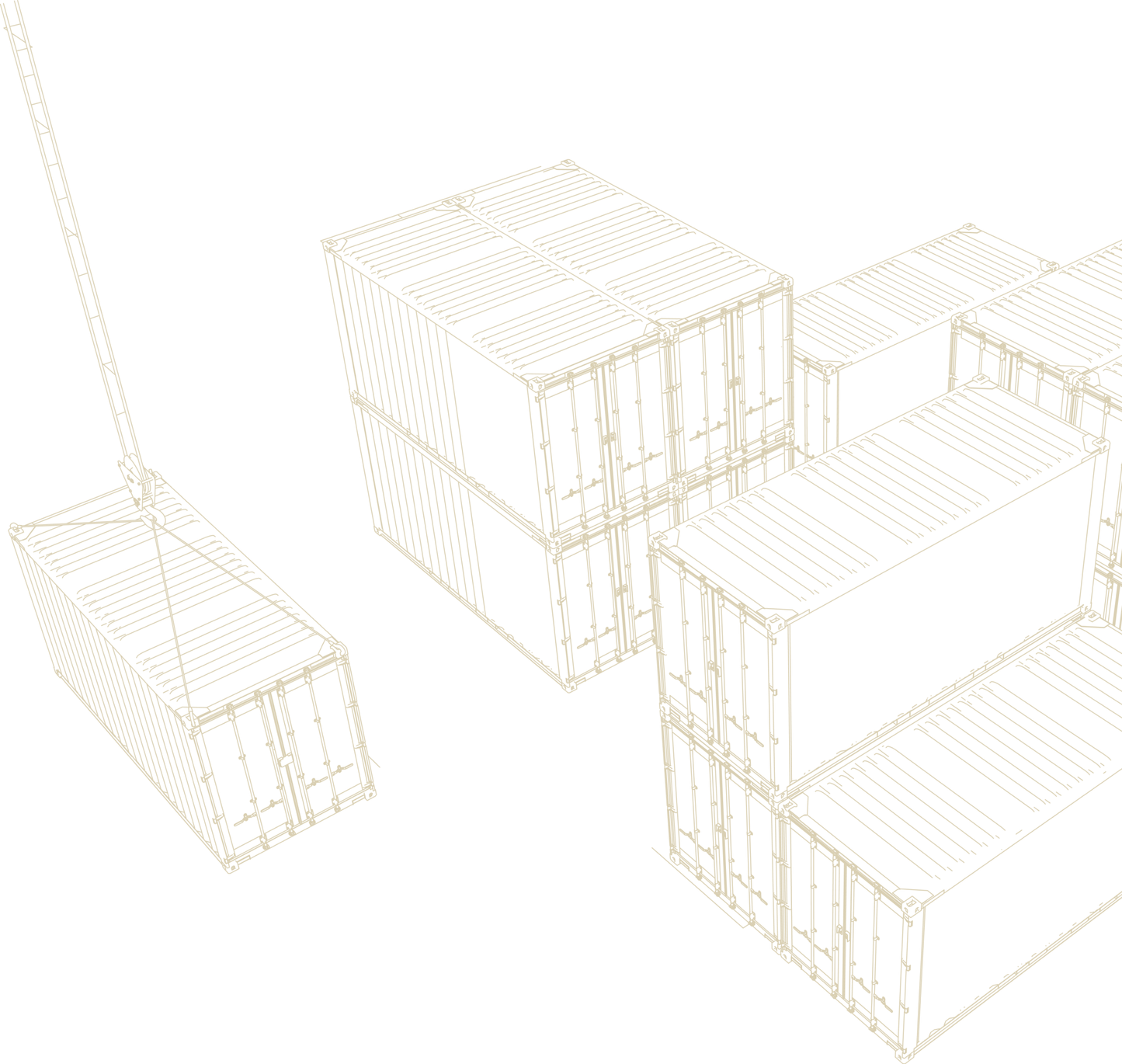
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
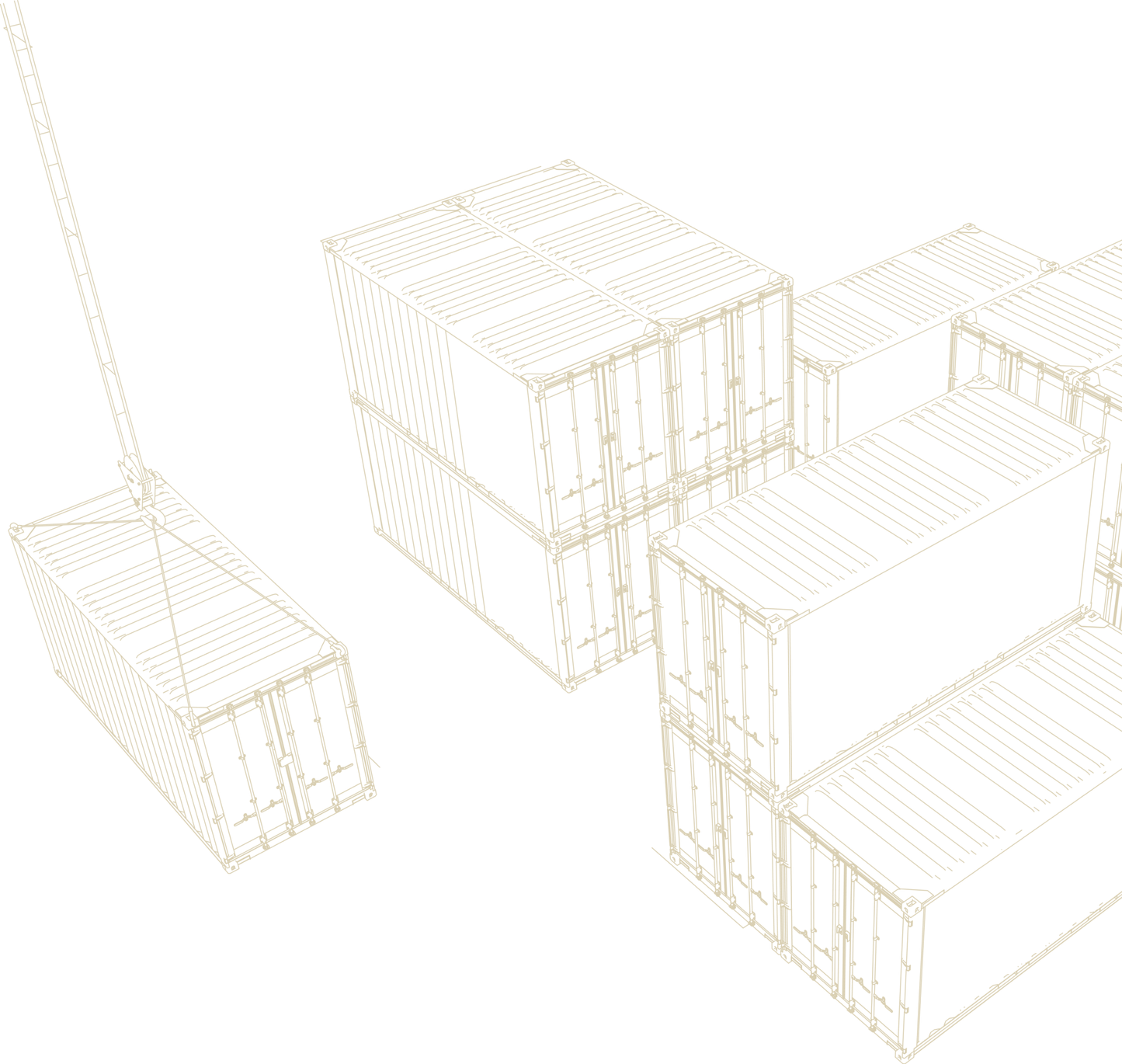
“世界を変えたのは「箱」の発明だった”
「コンテナ物語ーマルク・レビンソンー」
日本酒のこれからを変えるには「容器革命」が必要である。

Wild Goose Filling
の缶充填機
Wild Goose Fillingの
缶充填機
アメリカで高い評価を得るWild Goose Filling社の缶充填機を採用。溶存酸素の混入を徹底的に抑えています。液体窒素を点滴し充填することにより、日本酒本来の繊細な香りや深い味わいを守ることが可能です。酸化による品質劣化を防ぎ、長期間でも鮮度を維持。蔵元のこだわりをそのまま缶に詰め込み、アメリカ市場へ高品質な日本酒を届けます。輸出後も変わらない美味しさを実現する、信頼の缶詰め技術です。

徹底
コストカット
徹底コストカット
輸出と販売の全工程を自社で一貫してこなすことにより、無駄な中間コストを削減。さらに、缶詰めを採用することで、瓶に比べて輸送重量を大幅に軽減し、送料も大きく抑えられます。軽量で割れにくい缶は輸送の安全性を高めるだけでなく、コスト削減にも直結。高品質な日本酒を手頃な価格でアメリカ市場に届ける仕組みを整えています。コスト面でも品質面でも、蔵元様の海外展開を力強くサポートします。

蔵元直接訪問
缶充填サービス
安心
サポート体制
アメリカ国内での酒販免許を保有し、FDA申請をはじめとする煩雑な手続きも一括代行。さらに、現地在住の日本人スタッフがイベント運営をサポートし、文化の壁を超えたスムーズなコミュニケーションと確実な進行を実現します。地域特産展やプロモーションイベントなど、蔵元様の魅力を最大限に伝える場をしっかりサポート。輸出手続きから現地販売促進まで、安心してお任せいただける体制を整えています。
2024年9月10日、オハイオ州コロンバスにあるヒルトン・コロンバス・ダウンタウンで「Taste of Saitama 2024」が開かれました。このイベントでは、埼玉県の食文化や特産品が一堂に会し、日本酒やクラフトビール、うどん、そば、醤油、かりんとうなど、多彩な品々が並びました。会場に訪れた方々は試飲や試食を通じて、埼玉ならではの味わいや魅力を存分に楽しんでいました。私たちNOREN SAKEも、埼玉の酒蔵さんが手掛けた日本酒をアメリカに届けるお手伝いをさせて頂き、今回のイベントでは、輸出入手続きやコロンバス市との調整を担当。輸出手続きやFDA申請の代行だけでなく、現地でのイベント運営も支援することで、酒蔵の皆さんが安心して海外市場に挑戦できる環境づくりを目指しています。埼玉の日本酒がこうしてアメリカで注目され、新たなファンを増やしていく様子を見ると、本当に嬉しくなりますね。これからも、日本酒を通じて文化の架け橋となれるよう、一歩一歩進んでいきたいと思います。
2024年10月、アメリカ・カリフォルニアで開催された「Hokkaido Gourmet Faire 2024」。このイベントは、北海道が誇る食材や飲料をアメリカのバイヤーや飲食業界のプロフェッショナルに紹介する特別な場でした。日本の豊かな食文化を現地で体験できる機会として、多くの来場者で大盛況。NOREN SAKEは、このイベントに向けて北海道の生産者を全面的にサポート。輸出入の段取りからFDA申請の代行、アメリカでの荷受、検品、搬入まで、責任もってお手伝いさせて頂きました。さらに、イベント当日は現地でブース運営や製品説明を行い、北海道の魅力を直接伝えるお手伝いもしました。
生産者の皆様には製造や品質管理に集中していただけるよう、NOREN SAKEが事務手続きや輸送を一括してサポート。こうした包括的な支援により、北海道の美味しさをアメリカ市場に届けることができました。
現地でのプロモーション活動を通じて、北海道の特産品がアメリカで多くの注目を集め、商談やパートナーシップのきっかけを生み出しました。NOREN SAKEは、これからも日本とアメリカをつなぐ架け橋として、皆様の海外進出を全力でお手伝いしていきます。
2024年に開催された北海道新聞主催の「Hokkaido Gourmet Faire 2024」イベントでは、またまたNOREN SAKEも少しお手伝いさせていただきました。このイベントは、北海道の食材や飲料を国内外に発信する貴重な場で、多くの方にご来場いただき盛況だったと伺っています。私たちは、輸出代行やFDA申請のサポート、輸送や現地での荷受・検品・搬入といったバックヤード業務を中心にサポートさせていただきました。当日はブースでの運営や製品説明にも関わらせていただき、北海道の魅力を直接お伝えするお手伝いもできたのではないかと思っています。
こうした形で少しでも北海道の特産品が注目され、バイヤーや飲食業界の皆さまとの新たな出会いのきっかけになっていれば、とても嬉しいです。これからもNOREN SAKEは、生産者の方々や関係者の皆さまが海外市場でスムーズに活躍できるよう、できる範囲でお力になれるよう努めてまいります。




NOREN Sakeの出張缶充填サービスにより缶充填された日本酒は全てアメリカ、シリコンバレーに向けて出荷されます。アメリカ市場進出にご興味のある蔵主様からのお問合せ、お待ち申し上げます。